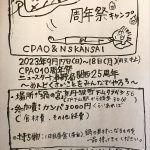周年祭キャンプ
2023年9月17日(日)18日(月祝)雨天中止
CPAO10周年&ニュースタート事務局関西25周年
~めんどくさいことをみんなでやろう~
場所:「渦の宮」京丹波下山クラベシ56(JR下山駅徒歩30分)
参加費:カンパ3000円くらいあれば(食材費、その他経費)
持ち物:一日目昼食(各自)、鍋の具材になるものを一品持ってきてください。
連絡先:ニュースタート事務局関西(高橋)090-6050-3933 email:info@newstart-kansai.sakura.ne.jp
※参加される方は上記まで必ずご連絡ください。
周年祭スケジュール
9月17日(一日目)
13時~16時 現地到着 準備
持参したお昼ご飯を食べながら、オープニングアクト
「CPAO沖縄姉妹」「引きこもり宣言」
一日を過ごす場づくり(火おこし、テント張り、飾りつくりなど皆で暮らし方を考える)
16時~19時 持ち寄り鍋の会
鍋の準備をしながら乾杯(引き続き場作りをしたり、遊んだり)
夕食と自己紹介的なことも
19時~21時 野外映画上映と話し合い
「めんどくさいことを手放さない暮らし(下之坊修子監督)」上映
映画の感想とそれぞれの「暮らし」について話そう。
21時~22時 野外フェス
うた、おどり、ラップ、ポエムなど
22時以降 引きこもりサミット
引きこもり25年「ひきこもり」とはなんだったのか
9月18日(二日目)
7時~9時 朝ごはん
朝ごはん準備、食べて片付け。ピザ生地をこねる
9時~11時 ピザ生地発酵中
ポカンとする人、遊ぶ人、引きこもりサミットの続きをする人
11時~13時 昼食
石窯でピザを焼いて食べる
(他にもやりたいこと、スポーツ、打ち水?など、いろいろ)
最後は、みんなで片づけをして、掃除
15時ごろ 帰宅
※室内では、伝説のメディアアクティビスト「てれれ」(2003年~2013年)のセレクト(略セ)と特集をほぼ24時間上映します(17日15時2003年セ、18時04年セ、20時コンドーム特集、21時05年セ、22時06年セ、23時07年セ、24時コミュニケーション特集、18日6時08年セ、7時09年セ、8時食と○○特集、9時テレビ特集、10時10年セ、11時11年セ、12時12年セ、13時13年セ)
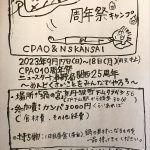

☆9月10日(日)夏のお楽しみ!持ち寄り鍋の会です☆12時~16時
暑い夏に一度は開催される持ち寄り鍋の会になります。これは暑い中鍋を食べる気にならない中考え出されたアイデアです(^^♪みなさん手作りの一品やお勧めの一品など何か持ち寄ってください。甘い物でも飲み物でも大歓迎です。こちらでも飲み物とおにぎりなど用意しておきます!
初めての方も是非ご参加ください!
※この時に9月17,18日に予定しているニュースタート(25周年)とCPAO(10周年)で一緒に「周年祭」をしようということになりました。そのことについての話し合いもしたいと思いますので、一緒に参加してくれる方もぜひこの日の鍋会に集まってください!
時間:12時~16時 第484回
場所:カフェコモンズ(JR摂津富田駅近く)
待ち合わせ:11時45分JR摂津富田駅改札口
参加費:カンパ制
参加資格:鍋会前か後に引きこもりを共に考える交流学習会に参加
※参加希望の方は必ず事務局までお申込み下さい。
9月の定例会◆(不登校・引きこもり・ニートを考える会)
9月16日(土)14時から (294回定例会)
場所:クロスパル高槻 4階 第4会議室
当事者・保護者・支援者問わない相談、交流、学びの場です。
参加希望の方は事務局までお申込みください。
詳細はこちら
※参加者は中部から西日本全域にわたります。遠方の方もご遠慮なく。
檄文~ニュースタート事務局関西25周年祭へ向けて
今から25年前に私たちの活動は「大学生の不登校を考える会」として始まった。同じ年、1998年、のちに「ひきこもり」という言葉(名詞)が定着するきっかけとなる「社会的引きこもり」が刊行される。著者の斎藤環氏が大学院時代に師事していた同じ精神科医の稲村博氏は、かつて「登校拒否症」という病気を作りだしていた。対して、奥地圭子(東京シューレ)氏が、1989年に「登校拒否は病気じゃない」と反駁していた。そして、ニュースタート事務局関西は「引きこもりは病気ではない」と掲げる。「大学解体」などをスローガンとする学生運動を経験した前代表の西嶋彰氏にとって、大学に通わない人(のちに「ひきこもり」と名指される人)の方が比較的まともで、何の疑問もなく大学の授業に出る学生や大学に行かないことを問題とする親の方に引きこもりの原因はあると、初めから直感されていた。のちの「ひきこもり」が大きな社会問題として扱われる理由は、一般には正しいとされる学校や職場などの社会や世間の側の問題であるからに他ならないという仮説だった。「大学生の不登校を考える会」に来る親たちは、「どうすればわが子をまた大学へ通わせることができるのか」「就職してくれるのか」などと、その方法について悩み相談には来るが、そこで共に考えることができるのは大学生の不登校がなぜ起きるかについてであり、なぜ就職できないかであり、それらはむしろ親自身や「ひきこもり」をも含む社会に原因があると確かめていくこととなった。引きこもり問題における自身の社会的責任や、親が子に向ける本来的な望みを自覚した親は、他所の子と交流をしたり、引きこもり問題に社会的に取り組むニュースタート事務局関西への協力などによって、初期NPO法人特有の活動や経済圏ができた。大学生の不登校など、引きこもる人は高学歴な人も多く、親はまだ中流階級以上の方が多かったため、引きこもりの社会運動は自助会やNPOなど、補助金や助成金などない形でも民間に多数存在した。だが、時は2000年代初頭、人口増による内需と経済植民地政策による外需のピークであった経済成長はバブルと共に終焉、オルタナティブな経済(地域通貨など)も模索しはしたが、圧倒的な新自由主義経済が猛威をふるい、金の自己増殖によって小さくローカルな試みのほとんどは焼け野原のように失われていった。私たちの引きこもりの社会運動は、身も蓋もない「支援」活動へと取って代わられることになる。「支援」やサービスが、対価やアリバイとなる行政主導の大きな経済圏が出現する。この「支援」が意味するところは、引きこもり問題は「ひきこもり」個人の病気や障害や能力や努力を問題として扱い、「ひきこもり」が社会復帰するために必要なことが問題となる。自らの原因を省みずに問う、問いを問いで返す解決しえない社会復帰問題が弾幕となり、引きこもり問題はすぐにも失われていった。それが私たちにとっての失われた30年問題だった。同時に「ひきこもり」という名詞が誕生し、名指され、「ひきこもり」と差別されることになる。ニュースタート事務局関西においても、親からの協力や寄付などの受け取りが変化していった。親や子も含めた引きこもり問題に取り組む活動(場を作ることや、個別に訪問することも含む)が、自分の子を社会復帰させるための支援やサービスの対価としての協力や寄付へと変わっていった。この経済において、目の前に出てきている「ひきこもり?」を個別に社会復帰させていくことが目的となり、引きこもり問題を社会へと追及するニュースタート事務局関西などの活動は表向きではなくなっていった。行政の下請けとして、補助金や助成金などの気まぐれで無尽蔵ともいえる金が「支援」を席巻し、これらの経済がなんの成果や評価もされない中、勝手な加速や減速を繰り返す。オリジナルな活動は消耗し、「支援」は後戻りもできない状況になった。2019年に、私たちは社会復帰するための「施設」となってしまう前に、「自治」という課題を残して共同生活寮(ドミトリー)を閉鎖した。
直後のコロナ感染、ウクライナ戦争、世界が引きこもる。そして、初心へと還る。90年代後半に日本社会に住む多くの若者が自室や家に引きこもるようになり、既存の社会で生きていくことが不安になった親たちが、子たちの引きこもる在り方を問題化したことによって、「ひきこもり」は明らかになった。そして、変わらないように見えた核家族や大企業や持ち家やニュータウン郊外やマイカーなどの既存の社会は、たかだか50年くらいしか続かない戦後のはりぼてでしかなかった。その時代の若者がそれぞれ病気や障害をもち、無気力や無能力な「ひきこもり」となったのではなく、不登校や就職氷河期など社会の歪に、引きこもる人たちが現れたと考える方が自然である。「ひきこもり」が日本社会の外にあって、その「ひきこもり」を社会の内へと復帰させなくてはならない、包摂しなくてはならないと考えるのは不自然である。「ひきこもり」は元から社会に包摂されていて、引きこもり問題を通じて、社会自らが内側から変わっていかなくてはならなかった。変わらなくてはならないのは、「ひきこもり」ではなく社会であるはずだった。社会は引きこもりという社会問題で変わりたくなかったので、「ひきこもり」を社会復帰することを「支援」とした。引きこもっている人は、定義上も目の前には表れないので、スケープゴートとするのにこれほど都合のいいことはなかった。社会という既成の器があって、「ひきこもり」を支援することによって、その「ひきこもり」を変え、社会へ復帰させることは、上手くいって既存の社会を強化することであっても、引きこもり問題が解消されることはない。むしろ「ひきこもり」を「支援」することにより、「ひきこもり」を産み出す社会を強化し、引きこもり問題がより強固になった30年であった。8050問題として騒がれていることはこの当然の結果なのであって、行政などが主導する「支援」構造を壊さない限り、どんなに手を施したところでどうしようもない。引きこもり問題は「ひきこもり」を包摂する社会の問題であり、「ひきこもり」を自分たちの社会の外へと差別化していることが問題で、「ひきこもり」を差別する社会や、支援者は「ひきこもり」と名指す自分自身と向き合わなくてはならない。「ひきこもり」は病気でもなければ障害でもなければ無能力や無気力の個人の問題ではない。hikikomoriが世界で日本社会を表象できるように、「ひきこもり」は私たちの社会である。そして、引きこもり問題を経由すれば、私たちの社会の様々な問題を考えていくことができる。「ひきこもり」が私たちの社会の指針となり、恩恵をもたらす。「ひきこもり」が、社会的でないのではない、自立できないのではない、責任がないのではない、労働できないのではない、勉強できないのではない、関わりがもてないのではない、孤立しているのではない。引きこもり問題を含まない社会が社会的でないのであって、それまでの既存の社会の自立や責任や労働や勉強や関係が間違いなのであって、孤立しているのは何も「ひきこもり」だけではない。「ひきこもり」の真価が問われるのはこれからだ。路上へと出て、今まで眼差されてきた私たちへの無気力な一瞥を、社会の内側から見返す時が来た。私たちも無力ならば、社会もまた無力。
2023年8月18日髙橋淳敏
「周年祭」
CPAO10周年&ニュースタート事務局関西25周年
~めんどくさいことをみんなでやろう~
2023年9月17日(日)~18日(月)
場所:「渦ノ宮」京丹波町
参加費:カンパ3000円くらい
{食費(一日目昼食と夕食鍋会もちより具材を除く)、宿泊費、その他経費にあてます。}
持ち物:一日目の昼食、夕食鍋の会に使う持ち寄り具材(例;肉、野菜、魚、豆腐、麺など)
各自一泊二日に必要なもの(例;タオル、歯ブラシ、着替えなど)
連絡祭:ニュースタート関西 電話:090-6050-3999
メール:info@newstart-kansai.sakura.ne.jp
スケジュール予定
9/17 朝:高槻出発→昼前:「渦の宮」着。各自持参の昼食を食べる。
夕食までの間やりたいこと(後ろに今出ているアイデアをまとめます。)
夕方:持ち寄り具材による鍋の会
夜にやりたいこと(同じく)
9/18 朝:みんなで朝食作り(おにぎりと汁物など)
昼食までにやりたいこと(同じく)
昼:石窯で手作りピザ
みんなで片付け→帰宅
祭りでやりたいことアイデア
・全員参加の制作物(看板、旗など)・映画上映「めんどくさいことを手放さない暮らし」
・引きこもりサミット・スポーツ・三線・踊り・打ち水・キャンプファイヤー、火おこし・ポエトリーリーディングなど。
何でも分からないことがあればお問い合わせ下さい。
9月10日の持ちより鍋会でも話し合いたいと思います。そちらにもぜひご参加ください。
 ニュースタート関西とは
ニュースタート関西とは